


伊丹市出身。自分が育ったこの街を、障がいを持つ方が幸せに暮らせる地域にしていきたいとの思いで2011年にあんさんぶるを立ち上げる。
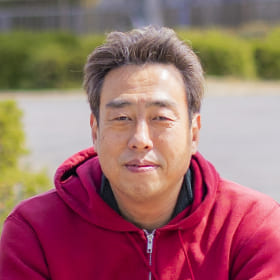
あんさんぶるがNPO法人から社会福祉法人への転換期にあった2021年入社。井ノ上理事長と共に、事業拡大に向けての組織改革に奔走している。
『介護職=低収入』というマイナスイメージへの違和感。
この現状を、変えなければ。
事業拡大のためにはスタッフの採用と定着が必須。その時、どんなことに力を入れましたか?
【井ノ上】 私は昔から、『介護職=低収入』というマイナスイメージが一般化していることにすごく違和感を感じていました。そのため、あんさんぶるの正規職員は、一般企業の同年代と比較してもひけを取らない収入にすると、スタッフに言い続けていました。だからなのか、現在では家庭を持つ男性スタッフも働いてくれています。収入に関する不満の声を聞くことはあまりないですね。
スタッフの高収入を実現するためにどんな工夫をしましたか?
【井ノ上】 端的に言えば、事業の多角化と仕事の効率化です。多角化という点では、日中の生活介護をするデイサービスだけではなく複数のサービス展開を目指しました。利用者さんの自宅への送り迎え、重心の方を対象とした放課後デイサービス、ご自宅での介護、移動や行動の支援、もちろんグループホームもその一つです。介護を必要とする方が、その一生を伊丹市で幸せに暮らしていくために必要な支援は、なんでも行っていくと決め、一つひとつ実行しました。
複数の事業を手掛ければ、それだけ法人の収益も増えるということですか?
【井ノ上】 その通りです。向上した収益はそのままスタッフの収入に直結します。
仕事が増えれば、現場の負担に直結するイメージがあるのですが…。
【井ノ上】 その点を払拭するために力を入れたのが、先ほどお伝えした『仕事の効率化』の工夫です。確かに、多岐にわたる仕事を個人が負担すれば、一人ひとりの負荷が増えます。その事態を避けるために、全員で仕事を分け合う仕組みが必要だと考えました。具体的には、一人の利用者さんに対し、誰が迎えにいくのか、施設では誰が付き添うのか、入浴は誰が担当するか、誰が送っていくのか、全てに対して細かく担当を設定し、分担して支援にあたる仕組みをつくるのです。そうすることで、個人に負荷がかかりすぎない仕事のやり方を確立しました。


そうすると、スタッフへの仕事の割り振りを管理する方も大変そうです。
【井ノ上】
作業分担はシフト管理のソフトで徹底管理しているのですが、確かに、管理者側も慣れるまでは苦労しました。一方に、さまざまな支援を必要とする利用者さんがいて、もう一方には、支援を担当するスタッフが複数人いる。誰がどの時間帯に何を担当すれば利用者さんが1日を気持ちよく過ごせるのか、まるでパズルのように組み合わせていくのです。
大変ですが、たくさんの人に支援を届けるためには、超えていかないといけないハードルだと思っています。
そうした時期を経て、現在は順調に事業を拡大しています。グループホーム開設の約束は果たしましたか?
【井ノ上】 立ち上げ当時は10年という約束でしたが、結果的に創業して9年後にはグループホーム「しゃるーる」を開設できました。採用への注力と働く環境へのテコ入れが功を奏して、スタッフ数も順調に増えていきました。グループホームを開設できたことは、創業からの一つの節目になりましたし、当初にご協力をいただいた親御さんたちのお子さんをグループホームに迎えることができました。
